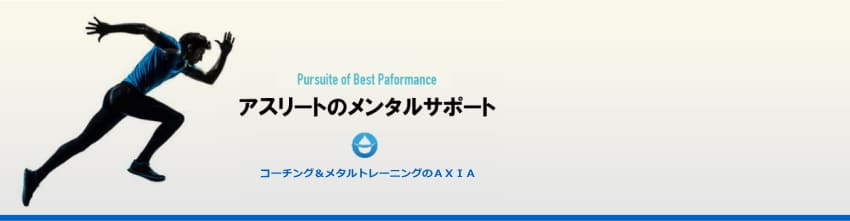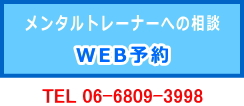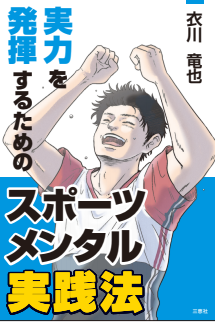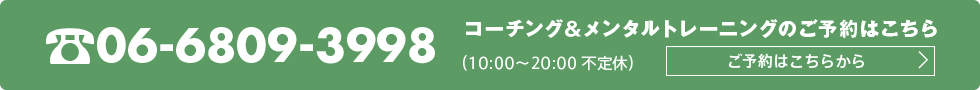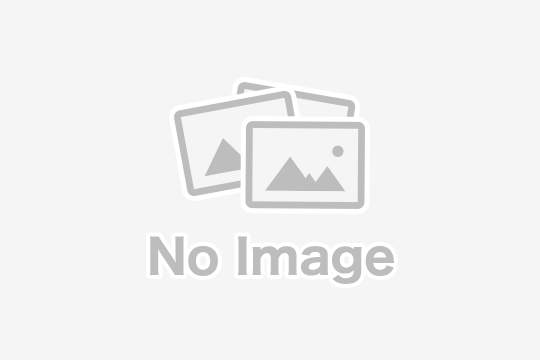「体罰は良くない」という認識だけでは体罰は止まらない
体罰がなかなかなくならない理由として、指導者の感情のコントロールだけでなく、本来指導とはどうかかわるべきなのかということに思考を巡らすことが少ないということも関係しているのではないかと思います。
スポーツや学校教育などで、子供たちを指導するということは性格や家庭環境の違う一人一人の子供と向き合い、相手のことを想像して接する必要があると思うのですが、人間はどうしても過去の体験から答えを探そうとする習性があるため、目の前の子供の性格や家庭環境という特有の条件をもとに、自分が取るべき行動を模索して接することよりも、自分が受けてきたり、見てきた指導方法を選択してしまう傾向があります。
指導とは何かという正しい認識が必要
指導というものは、その要素として教えることや伝えることが入っていますが、気付かせること、考えて答えを絞り出させることなども含まれています。
そのため、手をあげるという力を行使した対応ではなく、よく話を聴く、伝えるための言葉を選び、また話を聴くというやり取りの中で、気付きを促したり、考えさせる問い掛けをして成長に導いていくことが望ましいと思うのですが、自分自身がそういった対応をしてもらったことが少ない場合、どうしても自分の頭の中にある行動パターンで関わってしまうのです。
体罰は良くないということは、多くの指導者も頭では分かっていると思うのですが、それと同時に教えないといけない、わかってもらいたいという思いから、行き過ぎた行動になっているケースも少なくないでしょう。
指導者が、指導というものについての心理面の本質のようなものを学ぶ機会があって、腕力ではなく洞察力、コミュニケーション能力などの目に見えない力を使って指導して行けるようにしていくことも体罰防止のために必要なことだと私は考えています。
体罰を必要としない指導と指導者の成長
体罰をしないということも含めて指導者が指導力を向上させるためには、指導者自身が自分の内面と向き合う必要があると思います。
なぜなら心の働きが自覚できることで行動の制御もしやすくなるからです。
内面と向き合うというと少し漠然としていますが、具体的には下記のような視点で自分のことを考えることで自己理解が深まります。
- 自分自身の欲求の傾向を知っておくこと
- 自分のストレス耐性とストレスを受けた時の反応の種類
- 自分の価値観やビジョン
- 選手に求めていること
- 自分の人格形成の要因と過程
現在の自分自身を知ることで、理想とする成長のイメージとそれに伴う行動が見えてくるでしょう。
『体罰をしない指導者』を超えて『適切なアプローチで成長を支援できる指導者』を理想的な成長のイメージにすると自分の取るべき行動への認識も変わってきます。
体罰をしない指導とは指導者の姿で成長を促す指導
指導者は、子供や選手に成長を促す役割ですが、自分自身が成長するということに取り組んでいなければ他人を成長させることはできません。
指導者には、成長とは何かを実感して、それを言語化できる力が必要なので、自分自身が成長するための取り組みを通じて成長する実感を得なければならないのです。
成長とは何かを実感して言語化できるようになれば、おのずと体罰が不必要であることはわかるはずです。
自ら取り組み成長している自分自身は、体罰の力で成長してわけではないという感覚が得られるはずです。
それを子供や選手に置き換えた時、指導者からの体罰は必要かどうかの答えはおのずと出て来るでしょう。
指導者が体罰を止めるためには、指導とは何かという答えと成長するということの実感を持つことが必要です。
他人を指導する立場にある人は、この2つの必要性について考えていただきたいと思います。
体罰をせずに他人の成長を促せる力を持っている指導者は、指導とは何か、成長とは何かということに対して答えを持っています。
まとめ:体罰をしない指導者とは
体罰をしない指導者とは、「体罰をしないことを意識している」「感情を押さえて行動を抑制している」ということではないということは、この記事から理解してもらえたのではないでしょうか。
体罰をしない指導者は、人を成長に促すアプローチの方法を持っている指導者です。
そして、そのアプローチの方法の土台には、自己理解、他者理解、自己成長、言語力などがあります。
自分と相手のこと、その関係性を把握して適切な言葉を選ぶことができていて、言葉の背景には指導者自身が現在も成長しているという事実があるという人は、人の成長を促すことができるでしょう。
そのような指導者を目指すこと自体が、体罰を生まないことにつながるはずです。
そんな指導者が増えることを願って体罰に関する情報を発信しています。
=== 感情のコントロールに課題を感じているアスリートが対象 ===
心の知能指数と言われるEQ向上を目的としたメンタルトレーニングプログラム「ココロスイッチ」
================================================
================================================
instagramでスポーツ心理の知識、メンタルトレーニングの方法について情報を配信中